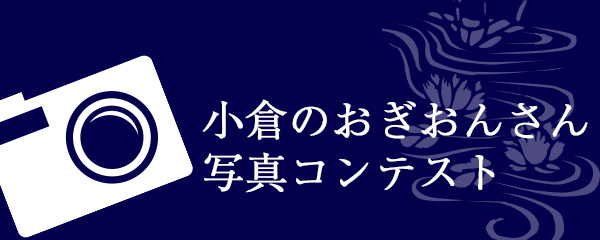2026(令和8)年の保存振興会行事は、詳細が決まり次第お知らせします
2026年度 日程
毎年7月
第3土曜日を含む3日間開催
7月1日(水)
- 山鉾すす払い
- 於:小倉北区役所
- 太鼓台開き【打ち初め式】
- 於:JR小倉駅小倉城口ペデストリアンデッキ
- 太鼓練習開始
7月17日(金)
- 宵祇園(初日)
- 山車巡行 於:小倉北区内各所
- 据え太鼓披露 於:市庁舎周辺
7月18日(土)
- 大賑わい(中日)
- おもてなし太鼓
- 子ども競演会(打ち手が中学生以下) 於:小倉城歴史の道
- 山車巡行 於:小倉北区内各所
- 据え太鼓披露
於:市庁舎周辺
7月19日(日)
- 打ち納め(最終日)
- おもてなし太鼓
- 太鼓総見(年齢制限なし) 於:小倉城歴史の道
- 山車巡行 於:小倉北区内各所
- 据え太鼓披露
於:市庁舎周辺
地域の太鼓広場
本祭の3日間、各地域では太鼓広場が開催されます。
詳細は決まりましたらHPでお知らせします。
お知らせ
-

- 2026.01.16
- 保存振興会委員会委員希望調査資料を会員ページにアップしました。
小倉祇園太鼓とは
小倉祇園太鼓(こくらぎおんだいこ)は福岡県北九州市の中心部である小倉で400年続いている「国指定重要無形民俗文化財」に指定された祇園祭である。小倉城を築城した細川忠興公が、城下の無病息災と城下町繁栄を願い、元和3年(1617年)に京都の祇園祭を模して始めたとされる。江戸時代は八坂神社の神幸行事としての「廻り祇園」が中心で、各町内が笛、鼓(つづみ)、鉦(かね)をはじめ、山車、傘鉾、踊車、人形飾り山などの出し物を、町内単位で披露していた。明治、大正時代を経て、山車の前後に太鼓を載せる現在の形となった。全国的にも珍しい太鼓の両面かつ歩行打ちが特長で、太鼓、ヂャンガラ(摺り鉦)、山車をひく子どものお囃子による一つとなった音の調和がすばらしい太鼓祇園である。
動画で見る小倉祇園太鼓
祭り紹介
小倉祇園太鼓保存振興会